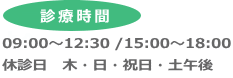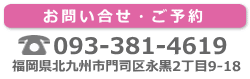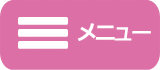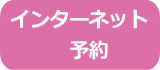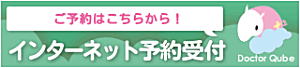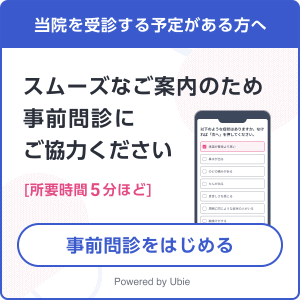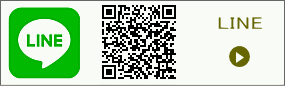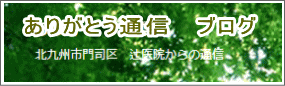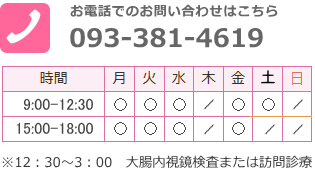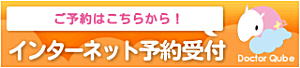慢性便秘症
 |
2017年に発刊された、国内初となる「慢性便秘症診療ガイドライン」によると、便秘とは「本来体外に排出するべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」と定義されています。
有病率は、50歳以下は、女性比率が高いですが、男女とも加齢とともに有病率は増加し、70歳以降になると男性の比率
が増え性差が無くなる傾向にあります。
慢性便秘は
に分類されます。 |
慢性便秘の診断基準
|
|
便秘の訴えで受診された方には、問診(症状、併存疾患、既往歴、家族歴、内服薬、生活習慣など)、腹部の診察、血液検査、腹部X線検査、腹部超音波検査、大腸内視鏡検査を状況に応じて行い、原因となる疾患や薬剤の有無、病型の診断を行います。 治療は生活習慣の改善、乳酸菌などのプロバイオティクス、症状や必要性に応じた内服薬を使用することです。 |