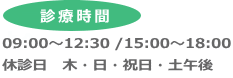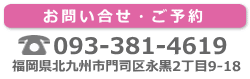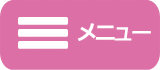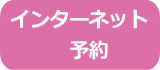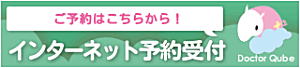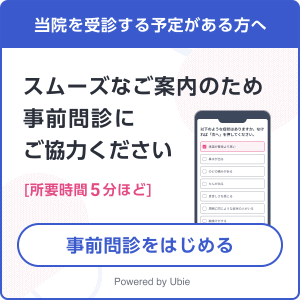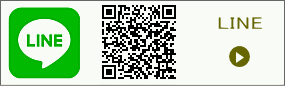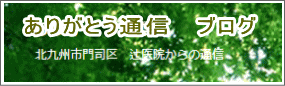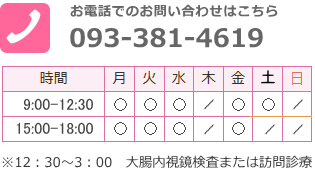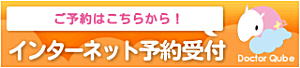逆流性食道炎
逆流性食道炎とは
 |
胃酸が食道に逆流し、食道の粘膜を刺激することで、炎症を起こした状態です。とくに、胃や食道の運動機能が低下している場合には、食道が胃酸にさらされる時間が長くなり、炎症が起きやすくなります。
胃酸が逆流する原因として、食道と胃の境目である噴門部(ふんもんぶ)の筋肉の力が弱まることで(食道裂孔ヘルニア)胃酸や内容物が逆流する場合や、肥満による腹圧の上昇などが挙げられます。
逆流性食道炎は、生活習慣も発症に大きく関係するため、治療では姿勢、肥満、食生活などの改善もあわせて行うことが再発の予防になります。
症状胃の中の酸が食道へ逆流することにより、胸やけ(胸の奥の焼けるようなひりひりする感じ、しみる感じ)や呑酸(口やのどに酸っぱい、あるいは苦い感じが込み上げてくる)、ものを飲み込むとつかえる感じがあるなどの不快な自覚症状が認められ、他にも慢性的なのどの違和感や咳の原因となることがあります。 |
検査内視鏡検査で食道粘膜の状態を確認し、炎症の有無や程度を正確に把握することが、適切な治療へつながります。さらに、逆流を起こしやすくする食道裂孔ヘルニアの有無や他の食道・胃疾患が無いかも確認できますので、内視鏡検査をお勧めいたします。 |
治療多くの場合、生活習慣の改善と薬物療法で効果があります。 生活習慣で気を付けること腹部の締め付け、前かがみの姿勢、右を下にして寝る(右側臥位)、肥満、喫煙などが原因となります。 食事面で避けたほうがよいこと食べ過ぎ、就寝前の食事、高脂肪食、甘いものなどの高浸透圧食、アルコール、チョコレート、コーヒー・紅茶・抹茶・濃い緑茶などカフェインが多いもの、唐辛子など刺激の強い香辛料、炭酸飲料、みかんなどの柑橘類などが挙げられます。 薬物療法
粘膜の状態や症状、他の基礎疾患などに合わせ、胃酸分泌抑制、食道胃機能改善薬などを適切に組み合わせて処方します。 胃酸の分泌を抑えるお薬が有効で、プロトンポンプ阻害薬(PPI)がよく使われます。わが国では、従来のPPIと比較してより強く酸分泌を抑えるとされるカリウムイオン競合型アシッドブロッカー(P-CAB)が使われることもあります。 8週間の内服で多くの患者さんの自覚症状は改善し、食道炎を治すことができます。 症状が強い場合やPPI単独で効果が十分でない場合に、消化管運動改善薬、漢方薬(六君子湯)を併用します。 |
||||